はじめに
「ぺこら烈士(れっし)」という言葉は、ホロライブ所属の人気VTuber・兎田ぺこらと、そのファンのあいだで生まれた特別な表現です。
本記事では、「ぺこら烈士」がどんな意味を持ち、どのようにして使われるようになったのかを、誰でも理解しやすい形で解説します。
兎田ぺこらという存在
公式プロフィール
兎田ぺこらは、2019年にホロライブ3期生としてデビューしたVTuberです。設定上は111歳のうさ耳の女の子で、人参が大好き。
あいさつは「こんぺこ!」という明るくキャッチーなフレーズです。こうしたキャラクター設定は、かわいさや親しみやすさを強調し、ファンが感情移入しやすいように作られています。
配信での姿
しかし実際の配信では、かわいいだけでなく、にぎやかで強気なキャラとして知られています。
甲高い笑い声や「いたずらっ子」的な一面が目立ち、視聴者を楽しませています。
一方で、コラボ配信では少し控えめで緊張する様子を見せることもあり、このギャップがさらにファンを惹きつけています。
また、ゲームに挑戦して失敗しても諦めない姿勢も大きな魅力です。
ぺこら語録
配信中に生まれた独特な言葉は「ぺこら語録」と呼ばれています。
代表的なものには「〜ぺこ」「きtらあああ」「はいぃぃ…」などがあります。
ファンはSNSやコメントでこれらを使い合い、仲間意識を共有します。こうした独自の言葉は、ファン同士の絆を強める役割を果たしています。
ファンコミュニティの特徴
「野うさぎ同盟」
ぺこらのファンは「野うさぎ同盟」と呼ばれます。
この呼び名には、単なる視聴者ではなく、応援する仲間同士が同盟を結んでいるという意味が込められています。
ファンは「自分たちが彼女を支えている」という自覚を持ち、コミュニティの結束力を高めています。
「ぺこ虐」という文化
ファンとのやり取りで有名なのが「ぺこ虐(ぺこぎゃく)」です。これは「ぺこら虐待」の略ですが、実際には愛情を込めてからかったり、失敗をネタにしたりする文化です。
もちろん本気でいじめているわけではなく、ぺこら自身もそれを楽しんでいます。このユーモラスなやり取りが信頼関係を深め、独自のファン文化を作り出しています。
兎田建設と「烈士」の誕生
Minecraftでの大プロジェクト
ぺこらは『Minecraft』の配信で「兎田建設」というプロジェクトを立ち上げました。最初は冗談でしたが、次第に仲間や他のメンバーを巻き込み、本格的な活動に発展しました。
テーマパークや便利な施設の建設、さらには大爆発を起こすTNTキャノンなど、その活動は多彩でした。
ファンが体験する試練
こうした配信は長時間になることが多く、単調な作業や予期せぬ大失敗が頻発しました。
それでも見守り続け、励まし、共に笑うファンは「烈士」と呼ぶにふさわしい存在です。
退屈や混乱を一緒に体験することで、ファンは強い絆と誇りを持つようになりました。
「ぺこら烈士」とは?
言葉の意味
「烈士」とは、本来、大切なもののために自分を犠牲にして信念を貫く人を指します。歴史的には「殉教者」のような意味を持ちます。ぺこらファンのあいだでは、彼女の配信の困難を共に乗り越え、長期間応援してきた熱心なファンを「ぺこら烈士」と呼ぶようになりました。
名誉ある呼び名
「ぺこら烈士」とされるファンには、以下の特徴があります。
- 長時間の作業配信を見続けた
- TNTキャノンの爆発などの失敗を見ても応援をやめなかった
- 「ぺこ虐」を理解し、一緒に楽しめた
- 苦境のときこそ支え続けた
この呼び名は、ファンの中で特別な「名誉」を表すものです。自分を「烈士」と名乗ることは、応援の歴史と誇りを示す行為でもあります。
まとめ
「ぺこら烈士」という言葉は、単なるファン用語ではありません。ぺこらが生み出す予測不能な混沌や試練を、ファンが一緒に耐え抜き、支え合ってきた証です。そこには、VTuberとファンがともに作り上げる新しいエンタメの姿があります。
つまり「ぺこら烈士」とは、ただ応援するだけでなく、困難すら楽しみ、仲間と一緒に乗り越えるファンを指す言葉なのです。

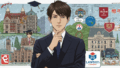
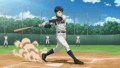
コメント